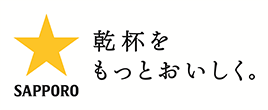互いの存在を知りながら「伊勢志摩サミット」で饗宴するも、当時は出会うことがなかったふたり。今回、「コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008」によって奇跡的なご縁が実現し、初対面を果たす。
2016年、ふたりは「伊勢志摩サミット」で出会うはずだった。
和紙デザイナー・堀木エリ子さんが「テタンジェ」のトップキュベ「コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008」のペアリングを体験する「食べるシャンパン」。
第1回目となる舞台は、風光明媚な三重県志摩市に位置する『志摩観光ホテル』内、「ラ・メール」です。2021年に70周年を迎える同ホテルの特徴は、伝統と革新にあります。このふたつを言葉にするのは容易いですが、そこには並々ならぬ努力と常に挑戦し続けてきた精神があってこそ。そんな両者のバランスは、「食」における領域が顕著に表れています。
牽引するのは、2014年より料理長に就任した樋口宏江シェフです。
自然と向き合い、豊かな地産の味わいを引き出す「伊勢志摩ガストロノミー」は、国内外からも高い評価を受け、数々の賞も受賞。中でも、大きな転機は2016年に開催された「伊勢志摩サミット」でした。
樋口シェフはワーキングディナーを担い、堀木さんは「ザ・クラブ」2階ホールの空間デザインを監修。巨大な一枚和紙から成る「光壁」という名の神々しい装飾は今なお輝き続け、それを一目見ようと足を運ぶ人も少なくありません。
しかし、お互いの存在は知るものの、当時、両者が出会うことはありませんでした。それが今回、約4年の歳月を経て「コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008」によってふたりは引き寄せられたのです。
「ご縁ですね」。
そんな堀木さんの言葉から始まりました。

樋口シェフが「コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008」に合わせて考案した料理、「東紀州、黒潮の恵み ガスエビを様々な形で」。ひと皿に表現されているが、一品一品を一膳に例え、それらを出汁がつなぐ。
-

「和紙も料理も自然から生まれます。当然、年によって生り物も変わるため、私はいただけた大切な食材をどうおいしく調理するかの責務をまっとうするだけです」と樋口シェフ。
-

「伊勢志摩サミットをきっかけにご縁をいただき、3年ほど前からガスエビを分けてもらえるようになりました。これまでは地元で消費されてしまい、流通に乗らない希少な食材でした」と樋口シェフ。

「伊勢志摩国立公園」の一部でもある英虞湾が目の前に広がる『志摩観光ホテル』。リアス式の海岸線が織りなす美しい景観は、今回の舞台でもある「ラ・メール」をはじめ、全室スイートルームの客室からも一望できる。
堀木エリ子のクリエイションに共鳴すべく創造された料理のペアリング。
「堀木さんがデザインされた“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”の日本限定ギフトパッケージの件を伺い、非常に刺激を受けました。産地への想い、職人への敬意、伝統を重んじる心、挑戦する姿勢、どれを取っても素晴らしかったです。今回は、ふたつのテーマをひと皿に込めました。ひとつは、生産者や地域への敬意や想いの表現。もうひとつは、和紙の四層漉きのごとく、同素材を4種のスタイルで味わう表現です。また、和紙という日本の伝統に寄り添うべく、あえて和の要素も取り入れました」。
そう話す樋口シェフが用意した料理は、堀木さんのテーブルに運ばれる前から豊かな香りが漂います。それが和の要素であり、正体は出汁。
「本当に良い香りですね! フランス料理に出汁とはびっくりです!」と堀木さん。
皿の上には3つの品とひとつの出汁。その全てを結ぶのは、三重県産のガスエビです。
「“東紀州、黒潮の恵み ガスエビを様々な形で”をご用意しました。まずは、ぜひお出汁から召し上がりください。三重県産の鰹とガスエビで取った出汁になります。鰹は伊勢神宮の神様に供える神饌にも使われています。昔からこの地は御食国と言われ、海産物が豊富に取れるので、神様の食事には鰹節が御膳の中心に配して備えられているほど大切な食材でした」と樋口シェフ。
崇めるその姿勢は、白い紙が神に通じると言われている日本の和紙の神聖な世界にも似ます。
以降、堀木さんの呼吸に合わせ、樋口シェフは料理を勧めていきます。
「崩すのがもったいないくらい美しい」と堀木さんが話すそれは、「ガスエビのカクテル」です。
「ガスエビを生で叩き、同じく三重県産のディル、レモンの皮と果汁、エシャロットを赤ワインビネガーでマリネしたものを塩とオリーブオイルで調理しています。ペッパーも効かせ、赤玉ねぎのピクルスとキャビアを添えて仕上げました」と樋口シェフ。
堀木さんは、満面の笑みを浮かべながら「これは、“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008” にぴったり! ひと口食べたら自然とグラスに手が伸びますね」。
「次は、ガスエビを大葉と一緒にパートグリックで包み、揚げた料理になります。添えてあるソースは、南伊勢のデコポンで作りました。皮も実も丸ごとピューレにし、柑橘のフレッシュと料理の香ばしさとシャンパーニュの相性も良いかと思います」と樋口シェフ。
「樋口シェフは、港や市場、畑などに足を運ばれているとお聞きしています。現場を知るということは背景を知るということ。それをお客様に伝えることで、よりその味が深まる。良い循環だと思います」と話しながらも、再びグラスに手が伸びる堀木さん。「やっぱり合いますね(笑)」。
「“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”の酸味、スパイシーさと非常によく合います。私は和紙を通してシャンパーニュとご縁をいただきましたが、更においしい料理とのご縁までいただけ、幸せです!」と言葉を続けます。
「最後は、ガスエビと大葉をリンゴで巻き上げた料理になります。リンゴはシロップで軽くコンポートしており、“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”と香りの同調を楽しんでいただければと思います。大葉の香りは日本らしく、海老との相性も良いです。上には花穂紫蘇を添えています」と樋口シェフ。
「切り込みが入れてあり、細やかな心配りは食べ手には嬉しいです。味だけでなく、香りのマリアージュも素晴らしいと思います。単品それぞれもシャンパーニュに合いますが、4品の流れも緻密に計算されていると感じました。食感、温度、甘味、塩味、旨味……。バランスが整っています。加えて、食材の物語も聞いて堪能できるという体験は、味の奥行きが広がります。手間暇かけて、現場に足を運び、生産背景も学んでいる樋口シェフの努力の賜物だと思います」と堀木さんは話します。
堀木さんの言葉を借りるならば、「見えることよりも見えないところが大事」。漁師や農家とのつながりができたことは、やはり「『伊勢志摩サミット』がきっかけでした」と樋口シェフは話します。
「ホテルという構造上、なかなか個人で食材を仕入れることの難しさがあります。しかし『伊勢志摩サミット』のご縁をいただき、三重県の食材を存分に活かした料理がテーマとして与えられました。今回、使用させていただいている食材は、ガスエビはもちろん、その時に出会った方々によるものが多いです。そのご縁に感謝する一方、より感じるようになったのは自然の変化。以前、ガスエビは春と秋が漁期だったのですが、年々不漁だと伺っています。その原因は、海水温度の上昇によるものだそうです。反面、これまで獲れなかった魚が取れたり、これまでいた魚の生育地域が変わってしまったり。人であれば暑さを凌ぐことはできますが、魚はそうはいきません。環境との共存も真摯に向き合わなければいけないと感じています」と樋口シェフ。
「料理、シャンパーニュ、ものづくりは、共通して同じことがあります。全て自然と向き合って作るものだということです。こんなふうに作ってみようと思っていてもその時の海の状態、ぶどうの状態、水の状態によって思い通りにはなりません。人間は自然には抗えない反面、偶然性によって生まれる感動もあります。お互い難しさを楽しんでいきたいですね」と堀木さん。

鰹とガスエビで取った出汁は旨味が満ち溢れる。「樋口シェフの料理は、日本人が作るフランス料理を土地のものを生かして表現していることが素晴らしいと思います」と堀木さん。味に奥行きを手伝うのは、葉野菜、香味野菜からの出汁。「一番手が抜けない品ですが、樋口シェフのお出汁はすごく手間暇かけて作られているのがしっかり伝わります」。通常はビスクなどで合わせるも、今回は堀木さんの和紙の世界に寄り添い、あえて和のエッセンスを加える。
-

ガスエビのカクテルを見て、「美しいですね。栄養素だけを得るためならば、綺麗な器や盛り付けは必要ありません。これは相手を思うおもてなしの心の文化。誰かが誰かを想う気持ちから生まれます。その心を樋口シェフからは感じます」と堀木さん。爽やかに香るレモンは、「ちょうど黄色くなりかけた青い感じの時期のものを使用しています」と樋口シェフ。「実は、今日も畑にお邪魔してきました」。
-

ガスエビを大葉と一緒にパートグリックで包み油で揚げた料理。ガスエビだけでなく、ソースに使用するデコポンも三重県産。主役脇役問わず、地産地消を演出する。
-

軽くコンポートした薄切りのリンゴでガスエビと大葉を巻き上げた料理。「“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”と香りの同調をお楽しみください」と樋口シェフ。
-

ペアリングを堪能後、「単品もさることながらこの3つの組み合わせ方は素晴らしかったです。食感、温度、甘みと旨みがそれぞれの調理法で最良に表現されていると思いました。ひと皿ですが4皿と同じクラスの料理は、全て“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”と寄り添い、互いを高める相乗効果を生んでいたと思いました」と堀木さん。
-

「“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”は味もさることながら香りも豊か。香りという視点では、お出汁。今回の料理は、味だけではない香りのペアリングも親和性を生んでいました」と堀木さん。
-

「“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”は、グラスに注がれた時の香りが素晴らしかったです。冷たい飲み物がこれだけ力強い香りを持っているのは驚きですでした」と、料理人らしい視点で自身の見解を話す樋口シェフ。
受け継がれる美学。背景を知ることで、初めて本質は表現される。
「実は私、両親が伊勢出身なのです!」と堀木さん。「父が斎宮、母が松阪なのです。小さいころから『志摩観光ホテル』にはお世話になっており、“志摩観(しまかん)”“志摩観(しまかん)”と呼ばせていただいておりました」と言葉を続けます。
『志摩観光ホテル』への再訪や供された樋口シェフの料理を通して様々思い出すも、特に印象に残っているのは第5代総料理長の高橋忠之シェフの言葉でした。
───
海の幸フランス料理「火を通して新鮮、形を変えて自然。」
火を使って、あるいは形を変えてより新鮮に、より自然に変えることは、素材に対する祈りである。
著書「美食の歓び」より
───
「生でもおいしいものは火を入れてもおいしい。今回、お料理をいただき、樋口シェフは高橋シェフの想いも受け継がれていると思いました。樋口シェフは、フランス料理の伝統を受け継ぎ、『志摩観光ホテル』の歴史も受け継ぎ、高橋シェフの想いも受け継がなければならい立場にあります。非常に重要な責務ではありますが、その背景を学び得た上で、ぜひご自身の美学に昇華していただければと思っております」と堀木さん。
「私は第7代になります。2014年より料理長をさせていただいておりますが、月日を重ねるごとに高橋シェフの偉大さを思い知らされます。『伊勢志摩サミット』は本当の意味で地域を知り、つながるご縁をいただけたと感謝しています」と話す樋口シェフに対し、堀木さんは「自らご縁を広げた樋口シェフの“パッション”があったからこそ。『伊勢志摩サミット』では顔を会わせることはありませんでしたが、同じ舞台で命をかけて表現した戦友のようですね」。
体験こそ価値。その土地で獲れたものをその土地でいただく。その土地で生まれたものをその土地で浄化させる。表現することと土地を知ることは一心同体なのです。
「土地で育ったという事実が大切。ガスエビがどんなに良くても別のところで育ったガスエビでは同じ味にはなりません。この土地で獲れたからこそ良いのだと思います。それが体験につながるのではないでしょうか。“コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2008”もまた、シャンパーニュ地方のグラン・クリュ(特級畑)に認定された5つの村で収穫したからこそのシャンパーニュ。フランス料理もシャンパーニュも和紙も自然とともに生きています。土地の声に耳を傾け、自然と生きる樋口シェフは、あっぱれだと思います!」。

「ミシュランガイド愛知・岐阜・三重2019特別版」にて一つ星を獲得した「ラ・メール」。地元三重県産の食材に向き合い続ける樋口シェフの世界を堪能できる。「三重の食材の素晴らしさを取り入れた料理をご提供していきます。自然の恵みに感謝の気持ちを込め、つながる全ての思いがお皿の上に、お客様に届きますように」と樋口シェフ。
-

女性として表現者として、互いを敬愛する堀木さんと樋口シェフ。2020年、テタンジェは長女のヴィタリー・テタンジェが5代目に就任。顔こそ見えないが、実は3人の女性が今回の饗宴を果たしているのだ。
-

「伊勢志摩サミット」にて堀木さんが表現した「光壁」の前にて。「まさか堀木さんとご一緒にこの場に立てるなんて感謝しかありません」と話す樋口シェフに「ご縁ですね」と堀木さん。神々しい光がふたりを照らす。

-
ガスエビとテタンジェ。
皿に並ぶ3つの料理と出汁。
地元食材「ガスエビ」と
“コント・ド・シャンパーニュ” を
さまざまな形でペアリングさせたのは、
志摩観光ホテル「ラ・メール」の樋口シェフ。
2016年のサミットをきっかけに、
地元の食材と生産者、さらには自然環境と
深く向き合うことになったと彼女は言う。
環境の変化により、
水揚げされる魚も
毎年同じように手に入るわけではないという。
そう、料理もシャンパーニュも相手は自然。
人間の思い通りにはならない。
反面、偶然によって生まれる感動もある。
そんな「難しさを楽しむ精神」においても
伊勢志摩の食材とテタンジェは見事に
ペアリングされていた。
ラ・メール
-
住所
三重県志摩市阿児町神明731 『志摩観光ホテル』内
-
電話
0559-43-1211
- ラ・メール HP
堀木 エリ子
1962年京都生まれ。高校卒業後、4年間の銀行勤務を経て、京都の和紙関連会社に転職。これを機に和紙の世界へと足を踏み入れる。以後、「成田国際空港第一ターミナル」到着ロビーや「東京ミッドタウン」などのパブリックスペース、さらには、旧「そごう心斎橋本店」や「ザ・ペニンシュラ東京」など、デパートやホテルの建築空間に作品を展開。また、「カーネギーホール」(ニューヨーク)での「YO-YOMAチェロコンサート」舞台美術や、「ハノーバー国際博覧会」(ドイツ)に出展した和紙で制作された車「ランタンカー‘螢’」など、様々な分野においても和紙の新しい表現に取り組む。「日本建築美術工芸協会賞」、「インテリアプランニング国土交通大臣賞」、「日本現代藝術奨励賞」、「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2003」、「女性起業家大賞」など、受賞歴も多数。近著に『和紙のある空間-堀木エリ子作品集』(エーアンドユー)がある。