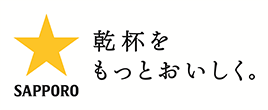- サッポロ 麦とホップ 特別取材 -
麦と、ホップと、
つくる人
『麦とホップ』。
原料名がそのままの、すごいネーミングである。
何かを足すのが新ジャンルだと思っていたが、
何も足さないのだ。
食品の安全・安心、原料の確かさが問われる今だからこそ、
このシンプルさが輝いて見える。
でも、そもそも「麦」って何?「ホップ」は?
どうやって「製品」に姿を変える?
名の知れたロングセラーだが、知らないことばかりだ。
『麦とホップ』を、徹底的に調べてみよう。
向かった先は、群馬、静岡、上富良野。
サッポロビールの、5人のキーマンを訪ねた。
取材・撮影 YOMIURI BRAND STUDIO

麦屋のプライド。
群馬県太田市。サッポロビール群馬工場の一角に、麦畑がある。風にあおられると、麦の穂がサラサラと心地よい音を奏でる。一見、普通の麦畑だが、近くで見ると、穂の丈や数、中にある種子の大きさや形などが、少しずつ違っていた。約5000種類もの育成系統(品種候補)が栽培されていた。
ビールは「麦酒」とも書く。大麦を発芽させて麦芽をつくり、それをさらに発酵させた麦の酒だ。麦芽の中に含まれるでんぷんやたんぱく質がビールの味わいの土台となる。
うまいビールづくりを追求するには、良い大麦づくりからスタートしなければならない。毎年毎年、畑で丹念に大麦を育て、観察することに加え、大麦の品種そのものを改良する、“育種”から手がけているそうだ。品種改良には結果が出るまで長い時間がかかる。その貢献を評価するのは難しく、国内大手ビールメーカーでも続けているのはサッポロだけだ。
バイオ研究開発部麦育種開発センターの斉藤渉は、「優れている品種同士を掛け合わせれば、成功するとも限らない」と語る。30年以上、品種改良を研究しているが、「今でも分からないところがある」という。
求められる条件は厳しい。地域ごとに栽培法は違う。日本(本州)では、秋にまいた種を梅雨入り前に収穫するので、生育の速度も重要だ。オーストラリアやカナダでは、乾燥に強くなければならない。十分な収穫量が確保できなければ、農家に栽培してもらえないので、品種として普及しない。
新たな品種づくりは、年に2回収穫して通常の倍のスピードで世代を進めるため、季節が逆になるニュージーランドと日本との間を何度も往復する。
穂が実る前の遺伝子検査で、「失敗作」と判定されることも珍しくない。ほとんどの育成系統が、実際にビールをつくるまでたどり着けない。いったん選ばれても、絶え間なく改善される。「そこを勝ち抜いた大麦だけが品種となり工場に送られるからこそ、我々は絶対の自信を持っています」。斉藤は言う。


麦育種開発センター長の廣田直彦は、自分たちのことを「麦屋」と呼ぶ。「ビールには麦屋にしか解決できない問題があるんです」。
廣田率いるチームが開発したLOX(ロックス)レス大麦がその一つの答えだ。LOXとは大麦に含まれるリポキシゲナーゼという酵素。ビールを長期間、保存していると、段ボールのような臭いが出て来る原因になる。泡持ちを悪くする要因でもある。
大麦の遺伝子分析など基礎研究を進めていた廣田に対し、「画期的な大麦をつくれ」との指令が下った。やり方は自由。すべては麦屋の発想力に委ねられた。「イネや大豆にはLOXを持たない品種がある。大麦にも同じような品種が存在するのではないか」。思いあぐねた廣田がたどり着いたアイデアだった。確証はないが、まずは手を動かしてみるしかない。
1万種以上の大麦を保存する岡山大からサンプルを取り寄せ、研究室に閉じこもった。種子を粉砕しては溶液を加え、酵素を分析する試験の繰り返し。インドの在来種にLOXを含まないタイプがあることを発見したのは、約2年後だったという。
だが、そのままでは醸造には使えなかった。世界各地の品種と交配を重ね、新品種として完成させた時、開発の着手から約10年が過ぎていた。廣田は「LOXレスは今後、世界のビール大麦の主流になる」と予想する。
サッポロからはこれまで、質の高さゆえ「奇跡の大麦」と称された「はるな二条」や、国内初のLOXレス品種「札育2号」など、画期的な品種が次々と生まれてきた。「麦からビールを良くしたい」。麦屋たちのプライドがサッポロの味を支えている。

ホップ畑の絆。
ホップとは、不思議な生き物だ。ハーブの一種だが、薬草としての特殊な用途を除けば、人類の歴史上、ほぼビールだけにしか使われていない。
その存在自体が、ビールのためにあるような植物なのだ。
ホップがビールの原料として広く使われるようになったのは、中世ヨーロッパから。ビールに、独特の苦みと香り、輝きを与え、保存性も高める。
どのビール会社もサプライヤーから上質のホップを仕入れるのに懸命だが、サッポロは、技術者が国内外のホップ農家を回って畑を見極め、
さらにホップ畑をつくって自ら育種まで続けてきたという。北海道上富良野町にあるバイオ研究開発部北海道原料研究センター長の大串憲祐は、「畑から始めるのがサッポロのビールづくりだと、教えられてきたから。それだけです」と話す。

大串はニュージーランドで、うれしい光景を見た。ホップは畑に設置したヒモを伝って、上へ上へとつるを伸ばしていく。だがその畑は、1メートルほどの高さより下の部分に、ホップの葉が全くなかった。向こう側の畑が見通せた。
ホップにはハダニが発生しやすい。地面から葉っぱを伝って上ってくる。そこで、その農家では、羊を放牧し、葉を食べさせていた。羊の口が届くのは1メートルくらいまで。その部分の葉がなければ、ハダニは上ってくることができない。「話には聞いていましたが、実際に見て、このホップ農家は信頼できるなと思いました」。
このやり方が他で通用するかどうかはわからないし、その土地、土地に合ったベストの栽培の仕方がある。「だから、一つずつ、見極めに行くしかない」。
腕に自信のある農家ほど、メーカーの人間が来るのを嫌がることがある。「買いたたきに来たんじゃないか、と思うんでしょう」。畑だけでなく、農機具庫などバックヤードも見せてほしいと頼む。「保管場所がきちんとしているかどうか見ながら話をしたい」。最初は話をしてもらえない場合もある。信頼関係が結べるのは、何度も通った後だ。「生産者には、ビールを持っていきます。これはあなたのホップでつくったんですよと。一緒に喜びを分かち合えるのがうれしいです」。

北海道原料研究センターでは、大串ら約10人のスタッフが、ホップの育種をしている。少し離れた場所に広々としたホップ研究圃場があり、毎年、数多い種類の品種や系統を育てている。
「開拓使麦酒醸造所開所の以前から100年以上、育種を続けていますが、まだ品種として、30品種は出していないんじゃないでしょうか」。交配してから品種登録をするまで、通常15年ほど。商品開発まで、さらに年月がかかることもある。こうしたホップ研究の成果が、チェコのホップを救ったこともある。チェコのザーツ地方は、ホップの品質で世界一を誇るが、1970年頃、ウイルスが原因で品質が低下、収穫量も減少し始めた。サッポロが技術指導して、1989年、ウイルスフリーの苗を作出。これを栽培した結果、もとの最高品質に戻ったという。
「10年後、20年後にどんなホップが求められるのか、だれにもわかりません。だからこそ、未来のお客様のために様々な品種を用意しておきたい。それに、ここで育てているのはホップだけではありません。同じホップに携わる人間として、農家と一対一で話ができる“人財”も育てているんです」。

夢見る工場。
麦やホップに関わる研究者たちは、自社の醸造技術に絶対の信頼を置いている。バトンを渡す先は、全国6か所に展開するサッポロのビール工場だ。その一つ、静岡県焼津市の静岡工場では、約19万平方メートルの広大な敷地に、巨大な発酵用・熟成用タンクが林立する。ここで働く約40人の醸造技術者をたばねるのが、静岡工場醸造部の阿部修也だ。2008年の発売から、合わせて四つの工場で『麦とホップ』の醸造に携わり続けてきた。「『麦とホップ』は麦原料100%とホップだけで製造されているのですが、シンプルだけに、原料の特性がそのまま出てしまう。それまでにない製法で、醸造も難しい。緊張感のともなうスタートでした」。素材がそのまま味になる『麦とホップ』だが、麦もホップも農作物なので、収穫時期によって品質は異なる。
醸造用の水や酵母の条件も毎回同じとは限らない。「そこが醸造技術者としての、腕の見せどころです」。
他の同様の商品の1.3倍も時間をかける長期熟成。ホップを3回に分けて麦汁に加える手間のかかる製法。それを続けさせるのは、「モノづくりの上で妥協はしない」という阿部ら技術者のプライドだ。


工場の敷地内には、研究開発部門である商品・技術イノベーション部の研究棟が併設されている。『麦とホップ』はここで誕生した。当時、ビール業界では新ジャンルの商品が相次いで発売されていた。同部の西尾真秀は言う。「そんな中で、改めてサッポロビールとして何ができるかを考えた時に、他社にはないこだわりを活かしたいと考えました。そこで、原料へのこだわりという原点に立ち返り、商品化に至ったのが『麦とホップ』でした」。
『麦とホップ』は、常に進化を遂げてきた。製造工程でのある現象の発見をきっかけに、仕込工程を見直したことで、品質と生産性が格段に上がったという事例もあった。これからもさらなるおいしさを目指すという。西尾は語る。「今回は、素材の配合などに工夫を加え、上質な味わいに仕上げました。麦原料100%とホップだけでつくるという、『麦とホップ』ならではの製法でないと、たどり着けないうまさがあります」。阿部も「まだまだおいしくなる」と話す。「ビール醸造の数千年の歴史に比べ、新ジャンルの歴史は10年余りなんですから」。

サッポロの前身となる「開拓使麦酒醸造所」が札幌に設立されたのは1876年(明治9年)。近代国家の建設に向け、北海道の開拓という大きな夢が託されていた。「北海道に新しい農業をおこすためにさまざまな農産物の試験栽培をする必要がある」。
醸造所建設の責任者だった村橋久成はそう主張し、屯田兵移民ら入植者たちの努力で、1880年には醸造所で使用する大麦のすべてを北海道産に切り替えることに成功した。今、サッポロは世界中から麦やホップを仕入れている。だが、畑から未来を見通す精神は、変わっていない。
麦、ホップ、そして製造の現場を訪ねてきた。そこには必ず、一貫したものづくりのポリシーがあった。「いい原料がないと始まらない。けれど、いい原料を使ったからといって、うまいものができるとは限らない」。各地のつくり手たちが一様に口にしていた言葉だ。担う役割は違う。でも、同じ思いがあるからバトンがつながる。「もっとおいしくできる」。ゴールは私たちの口元だ。
『麦とホップ』を改めて飲んでみる。サッポロの人と歴史から生まれた、結晶の味がした。

- サッポロ 麦とホップ 特別取材 -
麦と、ホップと、つくる人。
取材・撮影 YOMIURI BRAND STUDIO
-2018年春 取材-